別れは、人生の中でもっとも避けたい瞬間の一つです。
親、パートナー、友人、そしてペット——それぞれの存在が、私たちの生活に深い意味を持っています。
私は2023年5月に娘を失い、2024年に91歳の父を看取りました。娘を失った悲しみや苦しみから、いまだに立ち直ることができずにいます。
コロナ禍で大切な人を失った方、災害や事故、事件、病気などでかけがえのない存在を失った方もいらっしゃることと思います。
この記事では、私が自分自身の気持ちを整理するために調べたことを書き綴ろうと思います。そして、同じように大切な存在を失った皆さんと、一歩ずつでも前に向かって歩き出せるようになるまで、気持ちを共有できればと願っています。。
大切な存在との別れは、なぜこれほど心を揺さぶるのか
愛情と喪失の関係にある心理的メカニズム・・・私の場合
私が娘を失ってからは、ずっと喪失感と無力感が抜けません。
- 愛する存在を失うことは、「自己の一部」を失う感覚に近い
胸をえぐられるような感覚 胸に穴が開いたような気がするのに、ずっしりと重たくなったような感覚。 - 「後悔」「怒り」「無力感」などの複雑な感情が同時に押し寄せる
「あの時こうしていれば・・・」「なんで?」が頭の中をかけめぐる。 - 「時間が解決する」とは限らず、時間だけでは癒えない心の痛みもある
主治医からは「時間が最良の薬と世間では言いますが、時間では気持ちが癒えないということが、最近の医学界では常識になりつつあります」と言われました。
Q:あなたは今、どんな感情を感じていますか?言葉にできますか?
悲しみの感じ方は人それぞれ
- 涙が出ない人、逆に涙が止まらない人もすべて正常な反応
SNSの書き込みでは「涙が出ない・・・私は冷たい人間なのだろうか」という書き込みが少なくありません。それは気持ちが受け入れることができないからです。
私はとめどなく涙が流れました。買い物の際中でも、道を歩いている時でも。今でもそんな状態です。 - 「自分はおかしいのでは」と思わないでください。それが「正常」です
喪失直後に心を整えるためにできること
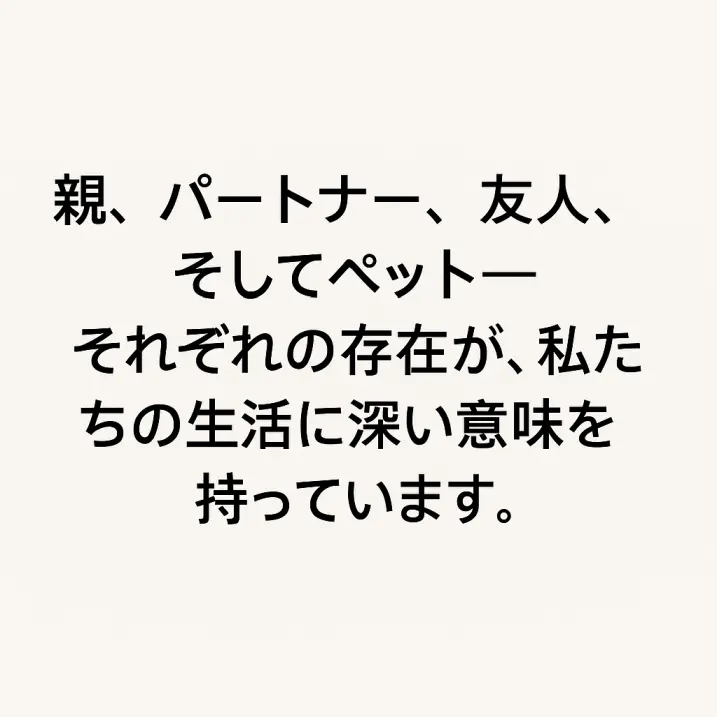
グリーフとは何か?海外の視点からの理解
グリーフケアについもいろいろと調べてみました。悲しみや苦しみから立ち直るプロセスを説明してくれています。ただ、私の場合、あまり役には立っていません。
- 「グリーフ(grief)」とは、失ったものに対する自然な反応
- アメリカ心理学会(APA, 2023年)によれば、グリーフは「プロセス」であり「病気」ではない
出典:American Psychological Association, 2023 - 複雑性悲嘆(Complicated Grief)は医療的支援が必要となるケースも
私が実践してみた3つの心のケア法
ネットで調べたところ、心のケアの方法がいくつか見つかりました。
- 感情を書き出す
来る日も来る日もパソコンに自分の気持ちを書きながら泣いていました。これは本当につらかったです。 - 信頼できる人にだけ、少しずつ話す
以前交流があった人たちとは会わなくなりました。娘の話が必ず出るからです。孤独感に悩む日々が続いたこともあります。最近は、少しずつ話せる人ができて、生活面でも助けてもらえるようになりました。 - 「悲しんでいい時間」を意識的に設ける
意識しなくても涙が止まらない日がたくさんあります。涙を止めることや悲しい気持ちを我慢することはしていません。
Q:あなたは誰かに話せていますか?
もし誰にも話せない状態でしたら、コメントで気持ちを伝えてみて下さい。きっと私と同じような気持ちでおられる方がいらっしゃると思います。
現実的に必要な対応リスト
家族だけでなく、家族同様の存在であるペットを失い、悲しみと苦しみの中で生活をされている方も多いと思います。
私の娘は猫をかわいがっていました。
猫が亡くなった時、バスケットの中に花をたくさん入れて、その上に亡くなった猫を寝かして泣いていたことを思い出します。
失って直後の一番つらい時期に、しなければならない手続きが山のようにありました。主なものだけ思い出して書き出してみました。
親や家族を亡くしたときに必要な手続き
- 死亡診断書の取得と死亡届の提出
父の場合老人介護施設に入所していたので、施設と提携している医師が作成してくれました。 - 火葬許可証の取得と葬儀の手配
これは火葬業者さんがやってくれました。大変助かりました。
ただし最近は火葬場が埋まっていてなかなか予約が取れないことが多いです。
父が他界したのは真夏でした。葬儀社の提案で「エンバーミング」という処置をしていただきました。ご遺体の痛みを防ぐ処置だそうです。エンバーミングについて詳しくは👉こちら - 年金・保険・銀行口座の凍結および相続手続き
まず最初にやるのは年金の停止手続きです。最寄りの年金事務所に予約を取ります。
銀行口座の凍結は一か月くらいしてからの方がよかったと思っています。
年金が停止前に振り込まれたり、引き落としが定期的にされているものを解約する必要があるからです。
口座の凍結をすぐやってしまうと、督促状が来たりします。この対応も数が多いと大変です。
ペットを失ったときの対応
- 地域のペット火葬サービスを調べる(自治体 or 民間)
- 遺骨の供養方法(自宅保管・合同納骨など)を検討
- 思い出の品や写真をアルバムにまとめて残す
友人やパートナーとの別れへの向き合い方
- 突然の別れでも、自分の気持ちに向き合う時間を持つ
- 「なぜあのとき…」という思いに区切りをつける方法:手紙を書く・儀式を行う
心の回復と社会との再接続
周囲とのギャップへの対処法
- 「少し落ち着きました?」「思ったよりお元気そうですね」と言われて、傷つくことがよくあります。
大切な存在を亡くした人にしかわからない苦しみがあります。 - 距離を取ってもいい、無理に話す必要はない
話すこと自体がつらいのです。人との付き合いをしばらくやめることも必要な場合があります。 - 自分を守る言葉を用意する:「話せるときが来たら話すね」など
私が少しずつ日常を取り戻すためにやった方がいいと言われること
- 毎朝10分だけ散歩する
私は20分を目標に朝散歩をしました。あまり効果はなかったように感じています。 - 故人の好物を自分でつくって食卓に並べる
これもつら過ぎてできていません。そもそも食事を取る気力がでません。 - 季節の行事を小さくでも続けていく
そんな気力は湧きません。
これからの生き方をつくっていくために
別れから受け取ったものを「継承」するとよい?
こんなこともネットで読みました。が、気持ちの整理にはなかなかなりません。
- 別れは終わりではなく、形を変えた関係の継続
たくさんの思い出が残っています。それは確かです。ただ、思い出が多ければ多いほど、苦しみは深いものです。 - 故人の価値観や言葉を日常に取り入れる
口癖などは思い出さなくても頭の中をぐるぐる回っています。 - その人が生きた証を、自分の行動で残していく
終活を始めました。あちらに行った時、土産話をたくさんできるようにと思いながら生活をしていますが、なかなか思ったようには進みません。
あなたの経験は、誰かの力になる
- 大切な存在を失った痛みは、他者への優しさの源になる
日本では、1日当たり3,944人の方が亡くなられているそうです。ふと道を歩いていてすれ違う方の中に、自分と同じつらさをかかえている人がいると思えるようになりました。知り合った方に、家族のことを聞くことはなくなりました。 - 同じ経験をしている人の「助け」になる可能性がある
そんなふうに考えて、このブログ記事を公開することにしました。 - あなたの経験を、誰かの「希望」に変えてみませんか?
もし私と同じようにつらい思いを抱えていらっしゃる方、つらい時期を乗り越えた方とコメントで交流できると嬉しいです。
よくある質問(FAQ)
Q. 悲しみが何ヶ月も消えないのはおかしいですか?
A. いいえ、悲しみの回復には個人差があります。1年経っても苦しさがあるのは普通です。子どもを失うのは人生で一番の苦しみだとか。立ち直るのに5年かかるというネット情報がありました。
Q. どうしても現実感がわきません
A. 「実感がない」ことも喪失反応の一つです。段階的に受け入れるプロセスを大切にしましょう。葬儀や四十九日が終わり、気持ちが一段落した時に、一気に悲しい気持ちが噴出すこともあります。
Q. グリーフケアはどこで受けられますか?
A. 心療内科や自治体の無料相談窓口、NPO団体などがサポートを行っています。遺族の会などがある地域を探してみるのもよいかもしれません。
関連リンク
今後順次ブログの公開を進めてまいります。

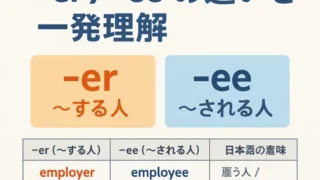











 癒しの色彩心理 イッセーのホームページ
癒しの色彩心理 イッセーのホームページ
